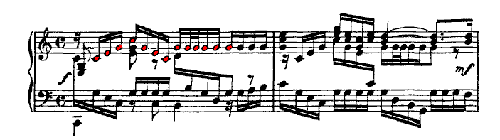
バッハの教会カンタータ
>カンタータ第119番
「市参事会」はドイツの自治都市にとって、年間最大のイベントの一つで、バッハにとっては豊富な予算と人員を利用できるチャンスでもあったようです。 バッハはミュールハウゼン時代に市参事会交代式用のカンタータ《神はいにしえよりわが王なり》BWV 71を作曲していますが、これは現存のカンタータの中で唯一バッハの生前に出版されたものです。 このように、この種のカンタータは、物質的には恵まれた条件で作曲に当たることができたわけですが、一方その内容は、為政者を讃える祝典的なものとなる他になく、ある意味で決まり切ったものになりがちであったと言えるでしょう。 このカンタータも少なくともその歌詞は、美辞麗句を並べ立てたもので、現代人が共感できるようなものではありません。「為政者は神の似姿」(第5曲アリア)など、あの悪名高いローマ書13章*にも、そこまでは書いてありません。
* 13:1すべての人は、上に立つ権威に従うべきである。なぜなら、神によらない権威はなく、おおよそ存在している権威は、すべて神によって立てられたものだからである。13:2したがって権威に逆らう者は、神の定めにそむく者である。(口語訳聖書より)
しかし、この作品はバッハがトーマスカントルに就任して、最初のこうした機会でもあり、音楽は華やかではつらつとしたものです。むずかしいことを考えずに存分に楽しめるものとなっています。さらに、曲の最後は敬虔なレシタティーヴォとテ・デウムで締めくくられ、浮ついた気持ちを抑えて、真剣に神と向かい合う終わり方になっています。
▼第1曲合唱曲は、こういう機会にふさわしく定番のフランス風序曲ですが、管弦楽組曲の何番だったかな?と思わせる音楽です。後で、演奏について述べるつもりですが、特にこの始まりの部分は一種の「けれん味」の音楽であり、誇張した所作や跳躍が面白いのです。(付点のリズム、1オクターブを駆け上がる装飾音、吹き抜けるトランペット、等々)。 中間部の合唱曲は、力のこもった、楽想が次々と湧き出してくるような音楽です。そして、先行する二つの部分を総合するように力強い管弦楽曲で第1曲をしめくくります。
詩編の引用を含んだ美辞麗句のレシタティーヴォ(T)に続いて、第3曲のアリア(T)は、2本のオーボエ・ダ・カッチャが美しくからみあう牧歌的な音楽で、「菩提樹の民」**たるライプツィヒ市民を讃えます。 しかし、そのまどろみも、次の第4曲レシタティーヴォ(B)に入り、時ならぬファンファーレによって破られてしまいます。
** ライプツィヒ Leipzigが11世紀初めに urbs Libziの名で歴史に登場して以来、Lipz、Lipskと転じて、Leiypzigkとなったのは15世紀末であった。Libziとはスラヴ語で「菩提樹の地」のこと。lipaといえば菩提樹のことである。 第119番のカンタータ第3曲テノール・アリアの歌詞に「菩提樹の民よ」とあるのは、この来歴を踏まえている。(ドイツ・シャルプラッテンTKCC-15182解説より)
続く第5曲アリア(A)は、アルトの声とリコーダーがからみあって、感じやすいメロディーを紡いで行きます。リコーダーのスタッカートは、このテキストに対するバッハの嘲笑を表すという説があるそうですが、現代人の考えすぎに他なりません。
▼さて、ソプラノの導入的なレシタティーヴォに続いて、このカンタータのクライマックスを形作る第7曲合唱フーガが始まります。これも第1曲同様、トランペットとティンパニが大活躍の曲ですが、ひたすらかっこいいと言うのみ。 なお、冒頭から、伴奏に「組曲第1番/ガヴォットⅡ」にも出てくる特徴的なファンファーレのメロディ***が登場し、それがより発展させられます。
ここまで、豪華絢爛フルコースというおもむきですが、第8曲レシタティーヴォ(A)に至って、美辞麗句は影をひそめ、敬虔な祈りが戻ってきます。そして、終曲コラールはルター訳のドイツ語テ・デウム****が簡素に力強く歌われ、質実な会衆の祈りで全曲を閉じるのです。
*** Oxford Composer Companionsによると、これは「ファンファーレテーマ」として知られているものです。下にBWV70冒頭のピアノスコア (リンク集にある"Free Sheetmusic Library"より)を示しておきましたが、 このテーマはBWV20:8, 127:4, 143:5, 214:3,7, 1046:1 etc.、その他テレマンのカンタータなどにも現れるそうです。
**** 〈Te Deum laudamus(神にまします御身をわれらたたえ)〉という言葉で始まる賛歌。最初の2語をとって呼ばれる。4世紀のミラノの司教アンブロシウスの作とする説,あるいはアウグスティヌスがアンブロシウスの手で洗礼を受けたとき,霊感に打たれた二人が,その場で交互に1句ずつ作ったとする言い伝えがある。(平凡社世界大百科事典より)
この曲の演奏については、このサイトのカンタータ録音一覧(BWV順)に10種類ほどの録音をあげています。それらについては、改めて述べたいと思います。
(2003年6月1日)
さて、演奏ですが、以下の録音を聞きました
Ramin 1953 EDEL BC 009099 Werner 1965 ERATO 3984-28166 Rotzsch 1974 EDEL 001829 Rilling 1978 Hänssler CD 92.038 Harnoncourt 1981 TELDEC H/L CANTATA 7 Koopman 1998 ERATO Koopman Cantata10 Herreweghe 1999 HMC 901690 Suzuki 1999 BIS CD-1131 Leusink 2000 Brilliant 99378/4 Pommer ???? CAPRICCIO 49 264 (第7曲のみ)
古い録音が豊富です。最初の4つと最後が従来スタイルのもの、残りの5つが歴史指向のものです。
▼まず、おそるおそるギュンター・ラミンの演奏を聞いてみました。ラミンは戦中戦後を通してのトーマスカントルで、カール・リヒターやヴァルヒャの先生に当たる人です。
しかし、これは大変立派な演奏でした。ソロ歌手達はまるでオペラのような歌い方ですが、合唱は怒濤の迫力があります。そして、レシタティーヴォを歌うボーイソプラノが可愛い!
器楽も全体にまずまずしっかりしています。アリアのリコーダーはフルートで代用されていました。(同じCDに収められているBWV 106ではリコーダーが使用されています。)
全体に古くさいのはしかたがありませんが、これぞドイツのバッハという感じでした。
フリッツ・ヴェルナーになると、私の年代には慣れ親しんだバッハの表現です。仮にこの録音だけしかなくても、このカンタータの良さは十分に感じることができるでしょう。 重要な役割を果たすトランペットは、おそらくモーリス・アンドレでしょう。(私のCDは廉価版で、そのあたりの情報が乏しい)。実に華やかです。
録音年代は10年ほど隔たっているのですが、ロッチュの演奏も基本的に同様のもの、と言う以上に伝統的なものです。
その響きは穏やかで心地よいものですが、同じトーマスカントルの演奏でもラミンほどのひたむきさが感じられない、というのは単なる気のせいでしょうか。
どこと言って欠点がありませんが、すべてが微温的で、少し退屈に感じることもあります。しかし、どっしりしたバランスの取れた演奏であり、一緒に歌いたくなる演奏とも言えます。
なお、3曲目のアリアのリズムは、楽譜では付点リズムのところを三連符として演奏するのが通例のようですが、この演奏は楽譜通りのリズムで演奏しています。
同じライプツィヒの演奏家を組織したポンマーの演奏は第7曲だけですが、名手ギュットラーのトランペットがさえ渡り、かと言ってむやみに突出せず、全体に生き生きした演奏となっています。
従来スタイルの演奏でも、リリングの演奏は、一つ一つの楽曲への切り込みが鋭いと言えます。第1曲冒頭の壮麗さを強調した表現、スピード感あふれる合唱部。 その効果はともかくとして、複付点での演奏はこれが初めてのようです。3曲目、5曲目のアリアは、かなりテンポが速く、のどかさは感じさせません。これも効果のほどはよく分かりません。 この二つのアリアは、今までと違う表現を追い求めて、かえって本来の姿から遠ざかってしまったような気がします。
結局、ここまでで、全体として一番まとまった演奏はヴェルナーのものでした。従来スタイルの演奏を聞いてきて、トランペットの妙技とか、ライプツィヒの合唱の響きとか、捨てがたいものはありますが、 これだけ歴史指向の名演がそろっている中で、独自の価値を主張するのはむずかしいのかも知れません。(歴史指向の演奏について、さらに続く。)
(2003年6月7日)
▼この作品に関しては特に、歴史指向の演奏を聞いて初めて作品の姿が現れて来ると思います。
個人的な感想ですが、昔のリヒターなどの演奏で、管弦楽組曲というものが全然面白くありませんでした。 そのため長らく敬遠していたのですが、最近の歴史指向の演奏ではテンポもリズムの取り方も全然違い、初めてその面白さが分かったように思います。 この作品でも、特に第1曲の飛び跳ねるようなリズム(いずれも複付点で演奏)、駆け上がる音階、総じて大げさな身振りの面白さは、従来スタイルの演奏のいずれからも感じることができませんでした。
個々の演奏では、まずヘレヴェッヘは文句の付けようがありません。合唱の緻密さ、自然さ、大胆さは驚きです。また、テノールのパドモアは入神の域。
またかと言われそうですが、一番好きなのはコープマンの演奏です。特に第1曲の飛び跳ねぶりが楽しい。そして、合唱の見事さはヘレヴェッヘ盤と双璧です。
鈴木盤は、楽器部分はほとんど聞き劣りしないか上回りますが、合唱に少し堅苦しい部分があります。また、コーイ以外のソロ歌手が少し弱いです。 しかし、以上3つの演奏はいずれも優れたもので、ほとんど好みの問題でしょう。
アルノンクール盤は録音年代も古く、とにかく今までとは違った行き方をしようとして、それが裏目に出た部分もあります。第1曲は速すぎ、第7曲は遅すぎなど、音楽として少し不自然なところもあります。 しかし、アリアはどちらも美しく、特に第5曲は今回のベストでした。(アルト:ポール・エスウッド、リコーダー:エリザベート・アルノンクール)
最後にレーシンク†盤は、技術的には上記に聞き劣りしますが、音楽の面白さ、美しさは十分に伝わって来るものでした。 テンポの取り方が適切で、よけいな工夫によって音楽を損なうことがないのがこの団体の一番の長所でしょう。(逆に言えば、余り考えすぎない。)
†Leusinkの発音ですが、以前に"alt.music.j-s-bach"で質問したところ(このニュースグループはオランダ人の参加者が非常に多い)、ドイツ語の「Oウムラウト」とほぼ同じという回答でした。 「Oウムラウト」は、日本語の「エー」とはまるで違う発音ですが、「ゲーテ」「ベーム」等と書き慣わしています。原音とは違うことを承知の上で、その習慣に倣って「レーシンク」と表記しています。
なお、第3曲のリズムは、コープマンとアルノンクールが三連符で、その他は付点のリズムで演奏していました。
(2003年6月8日)